
コンピュータで読み解く生命医科学の世界
バイオインフォマティクス技術を活用して新しい視点からがん医療に取り組む
奥田修二郎教授の専門であるバイオインフォマティクスとは、生命科学(バイオ)と情報科学(インフォマティクス)の融合で、生物が持っている情報をコンピュータで解析する分野だ。「ヒトの遺伝子数は2万個以上と言われています。それを解析するときに目視で数え、人の手で1つ1つ処理するのは現実的ではありません。コンピュータを使い、大量のデータからその意味や特徴を解析するために、バイオインフォマティクスの技術を応用しています」
ヒトDNA の全塩基配列を解読するプロジェクト「ヒトゲノム計画」で用いられた次世代シーケンサー(遺伝子の塩基配列を高速で解読する装置)が登場した2000年代中盤以降、生物?医学研究が加速度的に進展し、膨大なデータを処理するバイオインフォマティクスの存在感が増してきた。新潟大学医歯学総合病院でも、がんの原因となる遺伝子変異でがんを分類し、体質や病状に合わせた個別化治療を行うゲノム医療が行われている。バイオインフォマティクスによるデータ解析のニーズは高い。
「患者さんと直接接することはありませんが、治療のためのデータを処理するという点でバイオインフォマティクスは医療を支える重要な役割を担うと思います」
現在、奥田教授が進めている研究は、腸内細菌叢解析、がんゲノム解析、病理組織の画像解析、データベース開発の4つが大きな柱となっている。
「病理組織の画像解析により、がん組織の遺伝子変異や病態を推測するための研究を行っていますが、これに人工知能を用いてアプローチしていきたいと考えています。また、最近、がん発症の原因に、がん組織に共生するバクテリアが関連している可能性があることが分かってきました。これまであまり注目されてこなかった分野で、新しい視点でのがん対策につながればと期待しています。バイオインフォマティクスは他の研究分野の発展を下支えする縁の下の力持ちの存在になることが多いですが、データ解析を通じてがんの治療の改善や予防に貢献できたらと思っています。自身の研究推進と同時に人材育成にも力を入れ、医学部や医療全体を盛り上げていきたいです」
 人工知能で病理画像から遺伝子変異の状態を予測できる
人工知能で病理画像から遺伝子変異の状態を予測できる Mutational signature解析から腫瘍内細菌叢が原因の癌が示唆される
Mutational signature解析から腫瘍内細菌叢が原因の癌が示唆される

広くすっきりとした研究室。本分野では、医学部だけでなく、理工系学部出身者や社会人など、多様なバックグラウンドを持つ学生を求めている。
プロフィール

素顔
奥田教授が好むワイン。「バイオインフォマティクスの研究者として、発酵?微生物の観点からワインの組成をデータ分析したらおもしろそう」と思いながら嗜んでいるとか。写真は以前、ベトナム?ホーチミンに行った際に撮影したもの。
※記事の内容、プロフィール等は2022年11月当時のものです。
関連リンク
タグ(キーワード)
掲載誌
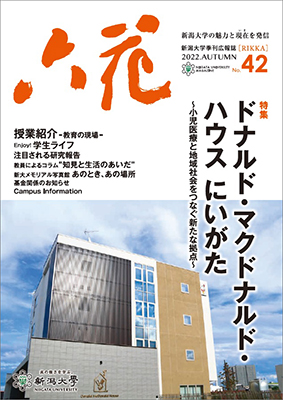
この記事は、新潟大学季刊広報誌「六花」第42号にも掲載されています。



